2025.11.25
SEO対策に最適なタイトル文字数は30字!?プロが解説するその理由



2025.7.25
Webライティング
インタビュー記事は、一見すると「話を聞いてまとめればできる」もののように思えるかもしれません。
しかし、実際には、構成で悩み、言葉の整理に詰まり、「何を伝えるべきか」がぼやけてしまうことも多いはずです。初めてインタビュー記事を担当する人にとっては、「どこから考えればいいの?」と戸惑う場面もあるでしょう。
この記事では、そんな不安を解消すべく、企画段階から質問設計、取材、編集、公開後の届け方まで、一貫して“読まれるインタビュー記事”を作るための手順を整理します。
本質は、「誰に、何を、何のために」届けるか。インタビュー記事は、ただ話を聞いて文字にする作業ではありません。読者に伝えるべき“意味”を探し出し、それが届くように形にする編集作業です。
ここから、各フェーズごとに実践的な視点を共有します。
目次

インタビュー記事を作るうえで、最初に考えるべきは「この人に話を聞くべきか」ではありません。
もっと手前の段階である、「誰に、なにを、なんのために届けたいのか」という問いに向き合うことが先決です。
読者像と記事の目的が曖昧なままでは、質問の方向性も構成の軸もブレてしまいます。「なんとなくこの人が面白そうだから話を聞いてみる」と進めてしまうと、いざ原稿を書こうとしたときに「で、結局何を伝えるべきか」が見えなくなりがちです。
まずは、紙にこう書き出してみてください。
この3点が明確になれば、聞くべきことが自然と見えてきます。
また、記事の目的が「採用広報」なのか「商品訴求」なのかによっても、引き出すべき情報や構成の流れは変わってきます。だからこそ、「誰に・なにを・なんのために」聞くのかを整理したうえで、はじめて“この人に話を聞こう”と対象を決めるのが順番として正しいのです。
この視点を持てるかどうかで、記事の完成度は大きく変わります。
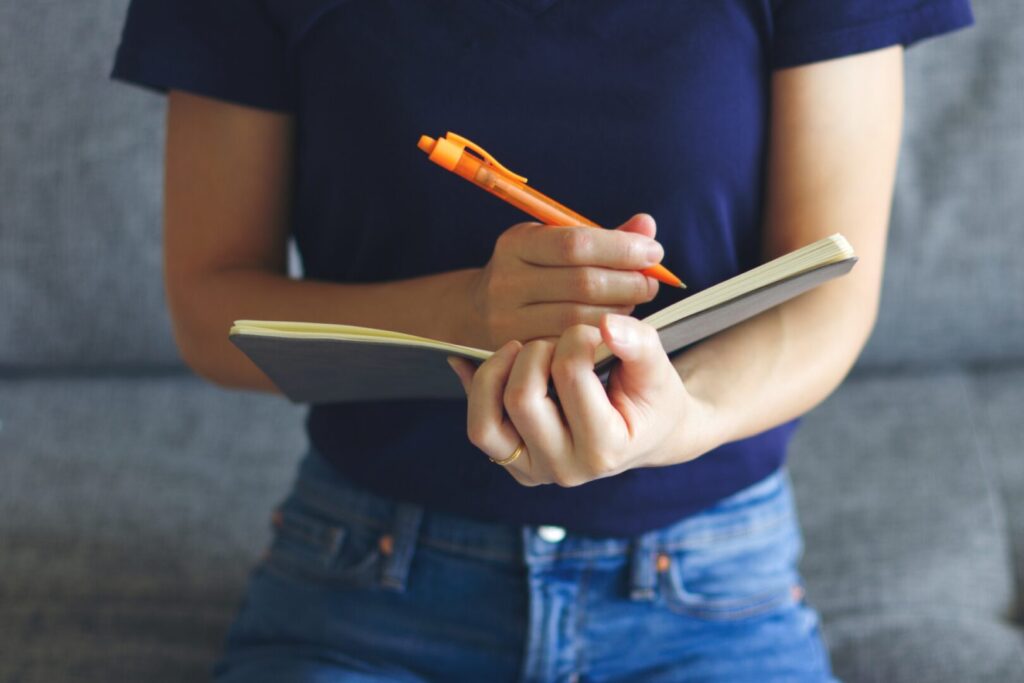
インタビュー記事が読み応えのあるものになるかどうかは、質問設計の段階でほぼ決まります。特に、一般の方を対象にしたインタビューでは、「どこから話を引き出すか」「どう掘っていくか」を質問で設計することが不可欠です。
質問は、ただ会話を進めるための道具ではありません。記事構成を逆算して設計する「骨組みづくり」です。最終的に読者に伝えたい“山場”や“メッセージ”を思い描きながら、それを引き出すための問いを組み立てていきましょう。
おすすめの質問の流れは、現在の状況を最初に聞き、現在に至るまでの過去の話を掘り下げ、未来の展望の話をするという流れです。
最初に、いま何をしているのか(現在)を聞くことで、相手も話しやすくなります。そこから、「なぜそうなったのか?」と過去に遡り、最後に「これからどうしていきたいか?」と未来を語ってもらう。この順序は、話の流れもスムーズで、記事構成にも転用しやすくなります。
事前に質問リストを相手に共有しておくと、より円滑にインタビューが進むので、おすすめです。準備時間があることで、話し慣れていない方でも安心感を持って臨んでもらえますし、「真剣に向き合ってくれている」と感じてもらえれば、取材への協力度も高まります。
質問の内容としては、「事実」だけでなく、「理由」や「エピソード」に必ず踏み込みましょう。
たとえば、「○○を始めた理由は何ですか?」と尋ねたあとに、「それって、どんなきっかけだったんですか?」「具体的にどんなエピソードがあったんですか?」と掘り下げていくようなイメージです。
WebサイトやYouTube、過去の登壇記録などから、事前に情報を調べておきましょう。そのうえで、「誰も掘っていない問い」を立てることができれば、インタビューの深みも読者の満足度も大きく変わってきます。

インタビュー当日に注意したい、コミュニケーションのポイントをご紹介します。
インタビュー当日は、空気づくりがすべてです。特に、話し慣れていない相手の場合は「話しやすい雰囲気」をつくれるかどうかで、その後の内容の深さが決まるといっても過言ではありません。
ポイントは「よく笑い、よく反応する」。話を聞く態度には、誠実さと素直さがにじみ出ます。無理に盛り上げる必要はありませんが、話にしっかり反応し、驚きや共感を声に出して伝えることが、相手の緊張をほどいてくれます。
加えて、リアルタイムで“掘る力”も重要です。 「なんで?」「どういう意味ですか?」と思ったことは絶対にその場で聞き返しましょう。それは読者の“なんで?”でもあります。
読者の代表としての視点を忘れず、その場での違和感を置き去りにしないことが、記事の完成度を高めます。

取材が終わったら、できるだけ早く素材を整理しましょう。時間が経つと、どの話が重要だったかの感覚が薄れてしまいます。
録音データを聞きながら、「構成に使えそうな話」「引用として強い言葉」をメモに抜き出していきます。文字起こしは、ただすべてを書き起こすのではなく、“整文”を前提に使う意識を持ちましょう。
そしてここで重要なのが、「録音の意味」です。 録音は単に“言葉を間違えずに書くため”のものではありません。録音を再生することで、インタビュー当時は気づかなかった意図や熱量が“稲妻のように”理解として落ちてくることがあります。
特に、インタビューを終えて、全体像が理解できている状態で序盤の話を聞くと、「あれはそういう意味だったのか」と、腑に落ちることがあるのです。
録音は、原稿を書くライターにとってのタイムスリップ。使わない手はありません。

インタビューが終わり、文字起こしを終えた段階で、いよいよ記事の構成を決めるフェーズに入ります。当初から構成を決めていることもありますが、インタビューの内容を踏まえ、修正を施すようにしましょう。
「話の流れをそのままなぞる」ことと、「読者にとって読みやすい順番に再構成する」ことはまったく別である、という認識です。
インタビューの会話は、どうしてもその場の流れや感情によって前後します。思いついた順に話されたことをそのまま並べても、読者にとってはわかりにくい場合が多くあります。そのため、インタビューは“原料”であり、記事は“料理された完成品”であるという意識が必要です。
構成の基本としても、「現在→過去→未来」の流れをおすすめします。冒頭で「この人は今、どんなことをしているのか(現在)」を示すことで、読者はスムーズに話に入っていけます。そのうえで、「なぜそうなったのか(過去)」をたどり、最後に「これから何をしたいのか(未来)」を語ってもらう。この流れは、自然なストーリー展開として読者に受け入れられやすく、記事全体の構造も安定します。
見出しは単なる区切りではなく、読者にとっての“次を読むかどうか”の判断材料になります。読者の視点に立って、「この見出しを読んだら続きを知りたくなるか?」という観点でつけていくことが重要です。
記事の冒頭にはリード文を置きますが、ここは記事全体の「要約」ではなく、「なぜこの記事を読む意味があるのか」を一文で伝えるパートです。読者の状況や悩みに寄り添い、「これは自分のための記事だ」と思ってもらえるような語りが理想です。
この構成設計の段階で、記事の読みやすさや伝わり方は大きく変わってきます。記事を書き始める前に、「誰に、どんな順番で、どんな温度で届けるか」を意識して構成を整えておくことが、読まれるインタビュー記事への第一歩となります。

インタビュー記事がある程度構成できたら、次は文章を磨く段階に入ります。このフェーズでは、「正確に伝える」ことだけでなく、「読者がストレスなく読み進められる」ことがとても重要です。特にWeb記事の場合、読者の集中力は紙媒体に比べて格段に短くなりがちです。だからこそ、読みやすさには徹底的に配慮する必要があります。
話し言葉をそのまま文章に起こすと、どうしても一文が長くなりがちです。長文が続くと、スマートフォンの小さな画面では読みにくさを感じさせてしまいます。一文は概ね40〜60字程度を目安に、必要であれば文を切り分けるようにしましょう。
インタビューの受け手がひとつの問いに対して複数の話題を語ることはよくあります。しかし、それをそのまま掲載すると、話が散らかって見えてしまいます。たとえば「朝食は何を食べましたか?」という質問に対して、「パンと味噌汁です。明太子バターを塗るのが好きで、最近はインスタント味噌汁も美味しいですよね」というような返答が返ってきた場合、それぞれの情報を分割して扱うことで、テンポの良い会話に見せることができます。
インタビュアーの“リアクション”も編集の一部として取り入れると、記事に臨場感が生まれます。読者は、書き手の「驚き」や「共感」を通じて、話の面白さを受け取りやすくなります。たとえば「えっ、そんなことがあるんですね!」といった一言が入ることで、単なる情報伝達にとどまらない記事になります。
さらに、言葉の温度を整えることも編集者の大切な役割です。敬語が不自然になっていないか、語尾のトーンが文章全体のテンポを崩していないかなど、文末のバランスも読み返しながら整えていきます。
文章を書いているとき、「この話、読者はすんなり理解できるだろうか?」「背景知識がなくてもわかるだろうか?」と自問しながら、必要に応じて補足や言い換えを加えるようにしましょう。読者に“説明不足”と思わせないことが、伝わる記事づくりに直結します。
インタビュー記事は、ただ話を整えるだけでは伝わりません。「この人の思いを、どうすれば読者にまっすぐ届けられるか?」という視点を持ちながら、文章を丁寧に整えていくことで、記事はぐっと深みを増します。

Web記事は“発信して初めて読まれる”ものです。たとえ素晴らしい内容でも、誰の目にも触れなければ存在していないのと同じです。この記事では、完成したインタビュー記事を「読まれる記事」に仕上げるための工夫を紹介します。
XやThreads、Instagramなどで記事が拡散されるとき、読者が思わずスクリーンショットを撮りたくなるような一文があるかどうかは大きな分かれ道になります。これは決して“映え”を狙うという意味ではありません。読者が「これは誰かに伝えたい」と感じる一文を記事の中に残せているかどうかという視点です。
具体的には、インタビュイーの語りの中でも「その人らしさ」や「独自の価値観」が端的に表れたフレーズを拾い出して、小見出しに使ったり、改行を挟んで印象的に見せたりする工夫が効果的です。
写真は単なる飾りではなく、読者の理解と感情を補強する視覚情報です。記事の構成に合わせて、写真の配置を意図的に行うことで、読みやすさや理解度が高まります。たとえば、熱量の高い発言に合わせてインタビュイーの笑顔を見せたり、話題に出たモノや場所を掲載することで、読者の頭の中に具体的な情景が浮かぶようになります。
1本の記事を「出して終わり」にせず、関連する過去記事へのリンクを設けたり、サービスページへの導線を設けたりすることで、読者の行動を自然に次のステップへつなげることができます。たとえば「この人のインタビューが気になった人は、こちらのイベント情報もチェック」といった形です。
記事の下部にCTA(行動喚起)を置くのも有効ですが、無理に押しつけるのではなく、「ここから先の情報をもっと知りたい人へ」という自然な流れとして設計することが大切です。
記事を公開したらインタビュイー本人にも共有し、可能であれば一緒に拡散してもらえるよう依頼しましょう。相手が記事に“愛着”を持ってくれると、SNSなどで自然と広がりやすくなります。
記事は、書き手だけのものではありません。話し手の言葉、編集の意図、そして読者の受け取り方が合わさって、ようやく完成します。「届ける」意識を持って最後まで設計することで、記事の価値はぐっと高まります。

企画の立て方、質問の構成、取材当日の進行、原稿化の工夫、編集、そして届け方まで――。
ひとつひとつが、どれも手間がかかるプロセスです。
しあし、それらをすべて通じて貫くべきものがあるとすれば、それは「読む人に届くかどうか」という視点です。
インタビューは、ただの情報収集ではありません。相手の熱量を受け取り、読み手にその熱を伝えるための、言葉の媒介装置です。だからこそ、「正確さ」だけでなく、「届き方」にも責任を持つ必要があります。
録音して文字を起こすだけでは、本当の意味で“伝わる原稿”にはなりません。その場の空気感、相手の言葉の背景、沈黙の重さ――それらすべてを踏まえて、読者が感じられるように言葉を編む。
それがインタビュー記事を仕上げる書き手の役割です。
ときには、相手の言葉を少し言い換えたり、話の順番を組み直したりする必要もあるかもしれません。
それは相手の意図を歪めるためではなく、より明確に、より深く伝えるための編集です。
書き終えたら、ぜひ一度読み返してみてください。
読者の目線に立って、「これで本当に伝わるか?」「この話を読んで、なにかが動くか?」と問い直してみてください。その一歩が、読まれる記事への最後の仕上げになります。
インタビューは、熱と信頼の交換です。言葉の裏にある思いまで汲み取り、それを“届く形”で整えていく。その工程にこそ、インタビュー記事を書く価値があります。
本記事でご紹介した内容は、実際に弊社、株式会社なかみでも日々取り組んでいる実践です。
「自社のインタビュー記事を作ってみたいけれど、どう始めていいか分からない」
「伝えたい思いはあるけれど、うまく言語化できない」
そんなお悩みをお持ちの方がいれば、ぜひ一度ご相談ください。
インタビューの企画設計から取材・執筆・編集・公開後の活用まで、
読者に“届く”言葉として仕上げるお手伝いをさせていただきます。
▶ ご相談・お問い合わせは 株式会社なかみの公式サイト からどうぞ。