2025.11.25
SEO対策に最適なタイトル文字数は30字!?プロが解説するその理由


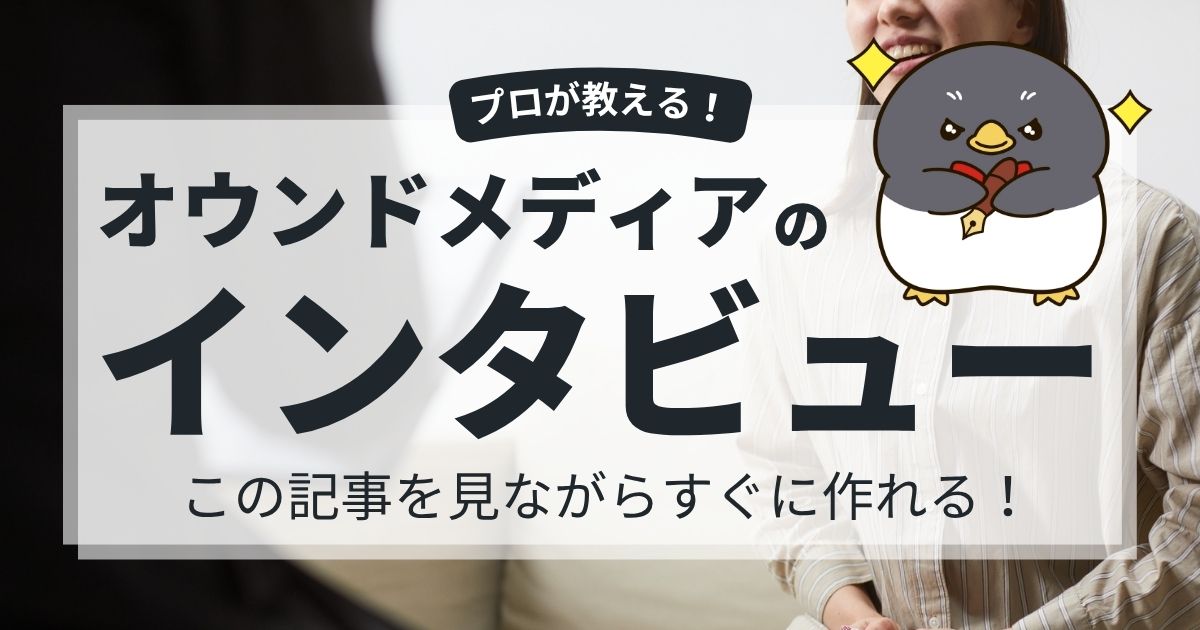
2025.11.17
オウンドメディア
オウンドメディアでインタビュー記事を作るかもしれない。でも、インタビューなんて経験がなくて、何から準備すればいいのかもわからない。
「質問ってどれくらい作ればいいの?」
「失礼にならない方法って?」
そんな不安を抱えていませんか。
この記事では、インタビュー記事の“最低限の正解ライン”をプロの取材経験をもとに、準備・当日・執筆の流れに沿ってわかりやすく整理。読むだけで、インタビューの進め方が一度でイメージできるようになります。
目次

インタビュー記事の作業は、準備・当日・執筆の三つに分けると全体像がすぐにつかめます。工程を一覧として見られるだけで、どこから始めればよいかが明確になり、作業の流れに迷いません。
流れは次のとおりです。
【準備】
・目的整理
・質問づくり
・事前調査
・アポ取り
・当日の共有事項作成
【当日】
・機材チェック
・アイスブレイク
・本題への導入
・広げる質問
・深掘り
・まとめの質問
・時間管理
・キーワードメモ
【執筆】
・録音整理
・要点抽出
・構成作成
・本文執筆
・校正
・事実確認
工程を横並びにして矢印でつないだ簡単なフロー図を手元で作っておくと、インタビュー全体の動きがひと目で理解できます。この一覧を自分なりにまとめておくことで、次に確認するべき“準備”の重要性がよりイメージしやすくなります。

インタビューの準備を進めるうえで、質問数・調査・アポ取り・ツール準備をどこまで整えればよいのでしょうか。それぞれ解説します。
インタビュー準備でまず整えるべきことは、質問・下調べ・アポ取りの三つです。この三つが揃うと当日の流れが安定し、会話の深掘りや時間配分で迷いません。
質問づくりでは、記事のゴールを決めてから質問を並べましょう。優先度を付けておくと、時間が足りなくても核心だけは確実に聞けます。調査では、相手のプロフィールや過去の発信を把握しておくことで、本題に入りやすくなり、自然な深掘りも生まれます。アポ取りでは、相手に安心して準備してもらえるよう、目的や所要時間を明確に伝えてください。
インタビューの質問数は、時間に合わせて決めると流れが安定します。30分なら5〜10問、1時間なら10〜15問が一つの目安です。これより多いと深掘りの時間が足りなくなり、逆に少ないと会話が途切れやすくなります。
質問は多めに用意しておき、優先度の高いものから順に使うようにしてください。すべてを消化する必要はありません。相手の話の流れに合わせて、必要なものだけを差し替えながら使っていくイメージで進めると、インタビューの流れが無理なく保てます。
質問は「現在 → 過去 → 未来」の順に並べると、相手が状況を整理しやすく、会話が無理なく進みます。最初に現在の話題を置けば、具体的な場面を思い描きやすく、入り口として適切です。
導入では、現在の取り組みや直近の状況を確認し、そこから過去の出来事や背景に移すと、話の全体像がつかめ、深掘りに向けた軸が定めやすくなります。
締めに未来の展望を聞くと、インタビュー全体を前向きな印象で終えられます。記事も同じ順序にすると、読後の印象が整いやすくなるので、おすすめです。
インタビュー前の調査は、まず公式情報から確認すると流れがつかみやすくなります。会社概要やプロフィールには、経歴・役職・事業内容が整理されており、当日の会話で迷いにくくなるためです。ここで土台を整えておくと、相手の説明を受け止めやすい状態をつくれます。
続いて、SNSや過去の記事に目を通してみてください。登壇情報や日々の発信からは“最近の動き”が読み取れ、長めの記事には価値観やこだわりがにじみ出ています。
注意したいのは、調査で得た内容を“結論”として扱うことです。事前に多く知っているほど、「きっとこういう話だろう」と決めつけやすくなり、思いがけない話題に気づく余裕が少なくなります。調査内容はあくまで“仮の理解”として置き、当日は本人の言葉で確かめる姿勢を保ってください。「どんな背景があるのか」「実際にはどう考えているのか」と順に聞いていく流れが、自然な会話につながります。
事前調査は、相手の情報を固める作業ではなく、理解の土台を用意する工程です。公式情報で事実を押さえ、SNSや過去記事で“らしさ”をつかみ、当日の会話に余白を残しましょう。このバランスが整うと、必要な話題に無理なく近づけます。
インタビューのアポイントは、目的と条件を最初の連絡で明確にすると進めやすくなります。相手が「何を依頼されているのか」を最初に理解できるため、返信までの負担が下がるためです。
メールでは、取材の目的や想定している所要時間、対面かオンラインかといった形式を簡潔に示してください。写真撮影の有無も前もって伝えておくと、相手が準備しやすくなります。候補日時を複数添えておくと調整がスムーズに進み、無理のない形で日程が決まりやすくなります。
依頼文の流れは、挨拶のあとに目的を述べ、所要時間と形式、質問概要、録音の扱いを知らせる形が扱いやすい構成です。候補日時を2〜3つ提示し、都合が合わない場合は別日で調整できることも添えておくと安心感が生まれます。必要であれば前日リマインダーを送ることも伝えると、丁寧な印象になります。
アポイントの段階で情報が整理されていると、相手は参加しやすくなり、当日のやり取りも落ち着いた雰囲気で始められます。依頼の伝え方が整うだけで、取材全体が滑らかに動き始めるはずです。

インタビューでは、事前にツールをそろえておくと当日の流れが安定します。録音や通信でトラブルが起きにくくなり、会話に集中しやすくなるためです。
対面での取材なら、スマホの録音アプリを基本にしつつ、ICレコーダーを予備として持っておくと安心できます。録音がうまく残らないケースもあるため、二つのデバイスで記録しておく形が安全です。ノートとペンを用意して、要点だけ手書きで残しておくと、後の構成づくりが滑らかになります。
オンラインの場合は、通信の安定が質を左右します。ZoomやGoogle Meetには録音機能が備わっているので、開始前に短くテストしてみてください。イヤホンマイクを使うと音の乱れが起きにくくなり、相手の声も拾いやすくなります。スマホやPCは充電を確保し、通知はすべてオフにしておくと集中しやすい環境がつくれます。
ツールの準備が整っていると、想定外のトラブルに振り回されずに進行できます。録音の安全、通信の安定、そして落ち着いて話せる環境。この三つを揃えるだけで、当日のインタビューがぐっと行いやすくなります。

当日は、入り方・質問の運び方・トラブル対応・録音とメモの扱いを押さえておくと、相手の話を自然に引き出せます。
インタビュー当日は、動き方を時間軸で押さえておくと落ち着いて進められます。会場に着いたら、録音や座る位置、周囲の音などを先に確認してください。スマホやICレコーダーを一度だけ試し録りしておくと、安心感が生まれます。
準備が整ったら、軽い雑談を交えて空気を整えます。緊張が残っていると話しづらくなるため、ここで穏やかな雰囲気をつくっておくと本編に入りやすくなります。その後で、目的や所要時間を短く伝え、録音を始める合図を入れると流れが安定します。
本編の進行は、序盤・中盤・終盤の三つに分けると整理しやすくなります。序盤は導入の確認、中盤は主要なテーマ、終盤は補足や確認にあてる形です。時間を区切って意識しておくと、焦らず進行できます。
撮影が必要な場合は、本編の前後どちらかでまとめて行うと段取りが整います。表情のカットや半身、作業風景など数パターン撮ることを想定し、相手が撮られやすい姿勢をつくれるよう声を掛けてください。撮影が苦手な相手には、角度や手元の作業カットなど負担の少ない方法を提案すると安心してもらえます。
終盤は、今日の話で確認しておきたい点を軽く整理し、原稿確認の流れを伝えて締めます。録音の保存を忘れずに行い、荷物をまとめて撤収します。その日のうちにお礼のメールを準備しておくと、全体の印象が丁寧になります。
当日の動きをこの順に押さえるだけで、落ち着いて本題に集中できる環境が整います。段取りに迷わない状態がつくれれば、会話の質も上がっていきます。
インタビューの序盤は、相手が話しやすい空気をつくる時間です。会場に入った瞬間から表情を柔らかくして迎え、軽い雑談を交えて緊張をほぐしてください。相手に余裕がなくても、こちらが笑顔でいれば空気がゆるみ、会話に入りやすくなります。
本題に入る前に、目的と所要時間を一度だけ短く伝えておきましょう。「今日は三十分ほど、現在のお取り組みを中心に伺えたらと思っています」のように、話す範囲を軽く示すだけで十分です。録音を始めるときも、ひと声添えると自然な流れになります。
姿勢は、胸を閉じない形を意識しましょう。そうすることで、相手の警戒がほどけやすくなります。手は机上に置き、頷きはゆっくり。視線を合わせて、相手の言葉に耳を傾けていることを伝えてください。特に話し始めの瞬間は、こちらの表情と頷きが“安全に話せる場”であることを示します。
序盤の十分は雑談や導入だけで終わることもありますが、この時間で空気が整えば、その後の深い話がスムーズに進みます。笑顔と姿勢を整えて、相手が自然に言葉を出せる土台をつくってください。

インタビューでは、質問の順番を整えておくと流れが安定します。最初に、相手が今どんな取り組みをしているのかを確認してください。現在の状況は答えやすく、会話の入り口として負担がありません。
現在がつかめたら、そこから過去の出来事や背景へ広げましょう。きっかけや当時の状況を尋ねると、相手のストーリーが自然に見えてきます。理由や工夫を聞きたい場合は、相手が使った言葉を拾いながら追加で尋ねると、深い話に入りやすくなります。
深掘りでは、理由・工夫・具体例の三つを押さえてください。「どんな理由があったのか」「どのように進めたのか」「実際にはどんな場面があったのか」という順番で聞くと、会話が散らかりにくくなります。
話題がそれたときは、一度受け止めてから戻すと流れが崩れません。「その話も興味深いですね。先ほどの〇〇の件に戻ると……」のように、相手の言葉を踏まえて誘導すると負担が少なくなります。
質問は、具体的な事実を起点にするのがコツです。そうすることで、ピントを絞った深堀りがしやすくなります。現在から始めて、過去・背景・理由へと深堀りしていく流れを意識しておきましょう。
インタビューでは、沈黙や浅い回答、話の脱線などが起きることがあります。どの場面でも、まずは慌てずに受け止めてください。相手が緊張しているほど表情が硬くなりやすいため、こちらが笑顔や柔らかい表情を保っておくと、空気が乱れません。
沈黙が生まれたときは、急いで次の質問を重ねず、少し間を置くと相手が続きを話しやすくなります。その間も表情は柔らかいままにしておくと、「急かされていない」という安心が伝わります。「ゆっくりで大丈夫ですよ」と添えるだけで、相手が落ち着いて考えられる時間になります。
答えが浅いと感じたときは、理由を直接求めるより、具体的な場面を優しく尋ねると深まりやすくなります。「たとえばどんな場面でしたか」「そのとき何をしていましたか」のように、負担のない聞き方で誘導してください。表情が硬いと“詰問”に見えやすいため、こうした質問こそ笑顔が効果を発揮します。
話がそれた場合は、一度受け止めてから本題へ戻すと会話が崩れません。「その話題も興味深いですね。先ほどの〇〇に戻ると……」のように、否定せずに方向を整えると流れが滑らかになります。長く続いた回答は、軽い整理を挟むと次に進めます。「まとめると〇〇という理解で合っていますか」と丁寧に確認してください。
困った瞬間ほど、聞き手の表情が場の空気を決めます。柔らかく構えておくことで、相手は安心して言葉を出しやすくなり、深掘りにも自然につながります。
インタビューでは、録音とメモの扱いを整えておくと、当日の会話に集中しやすくなります。録音は一つだけに頼らず、スマホとICレコーダーの二つを使うと安心です。開始前に短いテスト録音を行い、音が拾えているか確認しておくと、途中で焦る場面を避けられます。
メモは、固有名詞や数字など、後で確認が必要になる部分だけに絞ってください。会話を丸ごと書こうとすると、手元に意識が向きすぎて相手の表情が見えなくなります。視線を上げ、必要な瞬間だけ手を動かす形のほうが、相手は話しやすく感じます。
オンラインの場合は、通信状態が質を左右します。回線を一度だけチェックし、できればイヤホンマイクを使って音声を安定させてください。背景やカメラ位置も整えておくと、相手が気を取られずに話せます。
録音機材が見える場面では、相手が緊張しやすいため、こちらは柔らかい表情を保っておくと安心してもらえます。準備が整っていることを表情で示すと、会話が自然に進みます。録音とメモを最小限の負担で扱える状態をつくっておくと、聞きたい話に集中でき、深い内容も引き出しやすくなります。

インタビュー後は、読者が最後まで読みやすい構成に整えることがゴールです。構成づくり・要約・事実確認の三つを押さえると、読みやすい記事を迷わず仕上げられます。
インタビュー記事をまとめるときは、最初に全体の形を決めると迷わず進められます。基本は「導入・本文・まとめ」の三つに分ける構成です。読者は最初に“この記事は何を扱うのか”を知りたいので、導入では目的や背景を短く示してください。
本文では、会話をそのまま並べず、テーマごとに整理し直します。発言の流れは実際の順番にこだわる必要はなく、読者が理解しやすい順に置き換えてかまいません。現在の取り組み、過去のきっかけ、工夫や理由など、話題ごとに段落を分けると、内容がすっきり見えるようになります。
文章を組み立てる際は、一つの段落に一つの話題だけを入れると読みやすくなります。長い発言は意味のまとまりごとに分解し、どのブロックに入るかを判断してください。記事のゴールが明確になっていると、この整理が進みやすくなります。
最後のまとめは、読者の理解を軽く整える工程です。本編で語られた内容の“核”を短く示し、必要であれば次の行動につながる情報を添えて締めます。三つのパートを意識するだけで、全体の流れが整い、読者が迷わず読める記事になります。
インタビューを書き始めるときは、まず情報を絞り込むところから進めると整理が早くなります。読者が知りたい内容に関係する発言だけを残し、重複や脱線は思い切って外してください。数字や固有名詞のような事実の裏付けになる部分は残し、それ以外は記事の軸に合うかどうかで判断します。
必要な情報が見えてきたら、次は並べ方を整えます。会話の順番にとらわれる必要はなく、読みやすい流れをつくることを優先してください。テーマ別に分ける方法が扱いやすく、時系列や「課題→解決」の順に並べる形も使えます。印象的なエピソードを前半に置くと、読み始めの関心を保ちやすくなります。
文章に落とし込むときは、言葉を一度整えます。敬体に揃える、冗長な表現を削る、一文に詰め込みすぎないといった基本だけで読みやすさが変わります。言い回しを変えるときは、相手の意図やニュアンスがずれないように注意しながら調整してください。
要約と再構成は、会話をそのまま書く作業ではなく、読者が理解しやすい形に変える工程です。何を残し、どう並べるかが決まるだけで、原稿は大きく書きやすくなります。
インタビュー記事を公開する前には、事実関係と文章の整合を一度まとめて確認しておくと安心です。とくに固有名詞や役職、数字のような誤りが許されない部分は、必ず相手に確認を取ってください。確認依頼は事実に限定し、表現の調整や文章の仕上げは編集側で行うと作業が進みやすくなります。
本文の表記ゆれも、この段階で整えます。ひらがな・カタカナ・漢字の使い分け、数字の表記、固有名詞の統一など、読者が戸惑う要素を取り除いてください。同じ言葉が複数の形で書かれていると理解が分散するため、一つのルールにまとめるだけで読みやすさが上がります。
最終チェックでは、文章の流れを滑らかにすることを意識します。段落のつながり、誤字脱字、リンク先や名前の正しさを確認し、読み手が迷わない状態をつくってください。数字や名称は見落としやすいため、最後にもう一度だけ確認するようにしましょう。
SEOについては、見出しの明確さと読みやすさが基本です。キーワードを無理に詰め込む必要はありません。検索者の疑問に答えてあげられている、わかりやすい原稿を目指しましょう。段落を短く保ち、箇条書きを挟むと視認性が上がり、結果的にSEOの面でもプラスです。
公開前の丁寧な確認と校正が、記事全体の信頼性を支える土台になります。事実を正しく整え、読みやすい形に仕上げることで、安心して公開できる記事にしましょう。
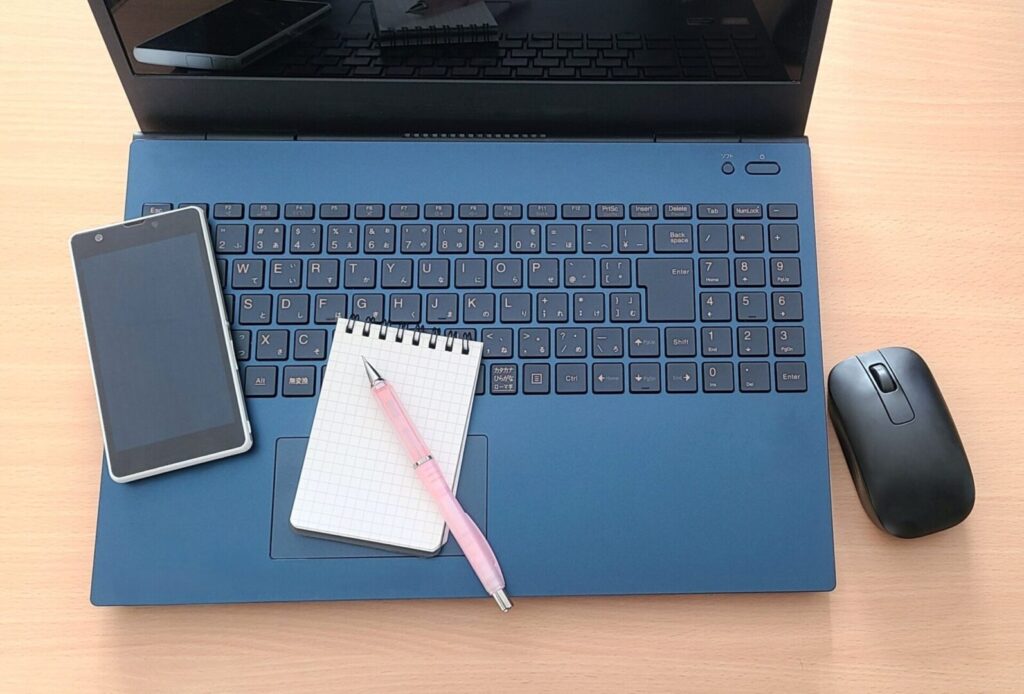
自分で進めるのが難しいと感じたときの判断軸と、プロに任せるメリット、そして弊社「株式会社なかみ」が提供できる支援内容までを整理します。
インタビュー記事を自分で進めるか、それとも外注すべきかは、作業のどこに不安があるかで判断できます。インタビューは、質問づくり・当日の進行・記事化という三つの工程で成り立っています。このうち一つでも迷いが強いと、仕上がりに影響が出やすくなります。
質問づくりで悩む場合は、会話の流れを組み立てるのが難しい状態です。どこから聞けば自然につながるのかが分からないと、相手の話が浅くなりやすく、記事の軸もぶれます。当日の進行に不安があるなら、沈黙や脱線にどう対応するかを想像できない段階です。会話の調整は経験の差が出やすいため、一番負荷がかかりやすい部分になります。
記事化に時間がかかる場合も、外注を検討する目安になります。会話をそのまま書くと長くなり、段落の整理や要点の抽出に時間がかかります。書く作業に慣れていないと、本業を圧迫してしまうこともあります。
社内にレビューできる人がいない場合も、判断材料の一つです。事実確認や文章の整えは、一人で行うと抜け漏れが出やすくなります。第三者の視点がないと、記事全体の品質を安定させにくくなります。
インタビューを外注すると大きな効果が出るのは、質問づくり・当日の進行・記事化のすべてに専門性が必要だからです。プロは記事の目的を踏まえて質問を組み立てるため、相手の話を深いところまで自然に引き出せます。読者が知りたい要点を軸に設計するので、最初の段階から会話がぶれにくくなります。
取材の場では、相手の言葉を拾いながら追加の質問を調整していきます。経験があるほど、どの部分を深掘りすると魅力が見えるのかが分かるため、対象者自身が気づいていない強みが浮かび上がることもあります。外部の視点が入ることで、主観ではなく“読者に伝わる形”に整えられる点も大きな利点です。
記事化まで一人が通して担当できる点も、プロに依頼するメリットです。取材で受け取ったニュアンスをそのまま構成に反映できるため、言葉の背景が途切れません。撮影や確認依頼、校正などの進行管理も含めて一つの流れで進むため、納期が読みやすくなり、品質の揺れも少なくなります。
質問設計・魅力の引き出し・一気通貫の制作。この三つが揃うことで、インタビュー記事は安定した仕上がりになります。初めて担当する場合や、重要な取材を確実に形にしたいときほど、プロの力が効果を発揮します。
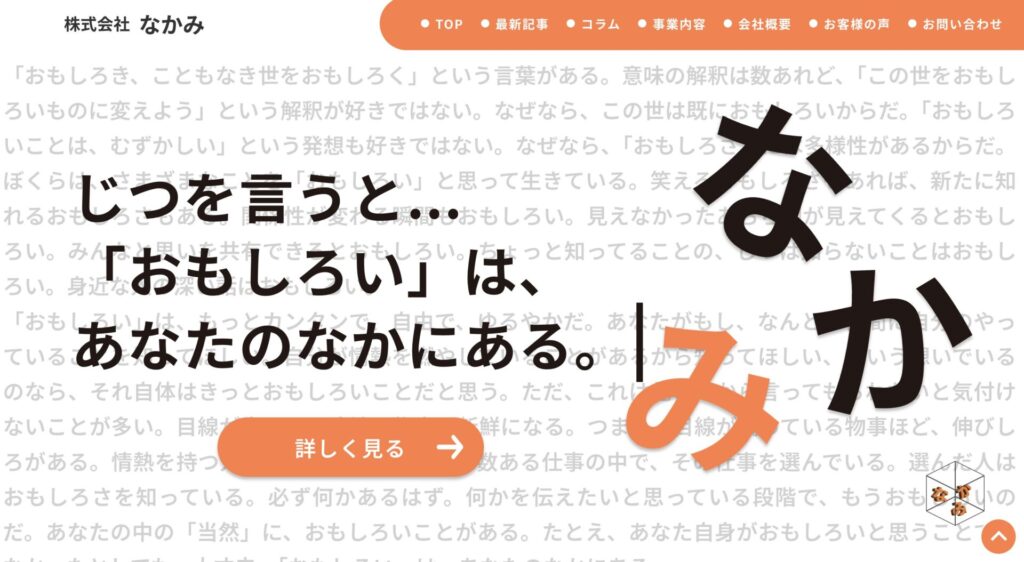
株式会社なかみでは、インタビュー記事の制作を最初の企画から公開まで一気通貫で対応しています。テーマの整理、質問設計、事前調査、取材、撮影、構成の作成、執筆、校正、事実確認、CMSの入稿、公開作業までをひとつの流れで扱うため、情報の抜けがなく、安定した品質で仕上げられます。
記事を公開したあとの運用も任せられます。アクセス分析や改善提案、追加記事の企画、SEOの調整、継続的な伴走まで対応しているため、インタビュー1本で終わらず、オウンドメディア全体の成長につなげやすくなります。公開後の動きが分かりづらい初心者でも、次に何をすべきかを明確に理解できる状態がつくれます。
初心者の方は、丸投げしていただいても大丈夫です。制作の各工程をなかみ側で進めるため、「何を用意すればいいのか」を心配する必要はありません。自社でできる部分を増やしたい場合は、質問案の作成や構成の進め方など、必要なポイントだけを部分的にサポートすることも可能です。
問い合わせの段階では、相談だけでも歓迎しています。企画が固まっていなくても構いませんし、検討段階の壁打ちとして使っていただくこともできます。まずは困っている点を聞かせてもらうだけでも、次に進む道を整理しやすくなります。
インタビューをどこから手をつければいいか分からない方でも、安心して任せられる体制です。必要に応じて頼る形で、スムーズに制作を進めてください。

インタビュー記事づくりは、準備・当日・執筆という三つの工程で進みますが、とくに成果を左右するのは準備の部分です。
事前調査や質問づくりで軸を整え、当日は表情を柔らかく保ちながら話を引き出し、録音とメモで情報を確実に残してください。記事化では、必要な情報を選び、読みやすい順に並べ替えると、内容がすっきりまとまります。
もし、質問設計や当日の進行、記事化に不安がある場合は、外注という選択肢も活用できます。プロに任せれば、深い話を引き出しやすくなり、安定した品質の記事につながります。株式会社なかみでは、企画から公開までの一連の工程を任せられるため、初めての方でも安心して進められます。相談だけでも歓迎しているので、迷ったら一度声をかけてください。
インタビューは経験を重ねるほど自然にできるようになります。この記事をもとに、自分に合った形で一歩を踏み出してみてください。