2025.11.25
SEO対策に最適なタイトル文字数は30字!?プロが解説するその理由



2025.7.24
SEO
「SEO対策をやっても成果が出ず、意味がないんじゃないか」と感じていませんか?
SEO対策が「意味ない」や「時代遅れ」などといわれる理由は、検索エンジンでの上位表示が簡単ではないからです。上位表示をするには、アルゴリズムを理解し、増えゆく競合のページよりも優れたページとして、Googleに選んでもらわなければなりません。
この記事では、SEO対策が意味ないといわれる原因や施策、成果獲得に向けたポイントなどに関して紹介します。SEO対策で長期間成果が得られず困っている方、オウンドメディアやECサイトの運用担当者の方は、最後までご覧ください。
目次

SEO対策に意味がないと言われている原因は以下の4つです。
自社サイトが検索エンジンの1ページ目に表示されない限り、検索流入の増加は見込めません。1ページ目に表示されたサイトで必要な情報を集められない限り、検索ユーザーはわざわざ2ページ目に進もうとは思わないからです。
検索順位が伸びない理由には、キーワードの選定ミスや検索意図の読み違えなど、さまざまな要因が考えられます。要因ごとに実施すべき施策は異なるため、成果が獲得できない場合はアクセス解析によって自社の現状を正確に理解することが重要です。
一定のアクセス数は見込めるものの、商品購入や会員登録など、事前に設定した成果を獲得できていないケースです。思うように成果が獲得できていない場合、掲載内容や訴求方法が合っていない可能性が考えられます。記事やページの内容がユーザーの検索意図に合っていない場合、ユーザーに「自身が求めている情報はない」と判断され、最後まで読んでもらえません。
ユーザーの購買意欲を高めるには、顧客がどのような情報や商材を求めているかを把握したうえで、自社商材の魅力を発信することが重要です。また、専門用語の多用や100文字以上の長文など、文章の内容や表現がわかりにくい場合も、ユーザーがすぐにサイトから離脱する原因の1つです。
知識の有無を問わずユーザーが内容を理解できるよう、わかりやすい表現で文章を作りましょう。専門用語を活用する場合は、用語解説の文を加えて説明を補足します。そして、スマートフォンユーザーが読みやすいよう、1文の長さは最大でも70文字程度に抑えましょう。
SEO対策は短期的な取り組みでは、成果獲得が難しいため、成果を得るまでに断念してしまうケースも珍しくありません。Googleの公式見解では、SEOを始めてから成果が出るまで4ヵ月~1年ほどかかると発表しています。新しいWebページや記事を作成しても、検索エンジンが認識・評価をするまでには数週間~数か月ほど必要です。
対策後にすぐに成果が出るとは限らないため、長期的な視点に立って取り組まなければなりません。
自社サイトの上位表示を実現できたとしても、Googleのアルゴリズムが変わった場合、急激に検索順位が低下するおそれがあります。アルゴリズムとは、特定のキーワードに対してどのサイトを上位に表示するか、検索順位を決める上でのルールです。Googleはユーザーの利便性を高めるため、定期的にアルゴリズムのアップデートを実施しています。
ただし、「ユーザーの検索意図に沿ったページ作り」を徹底してきた場合、大きく順位が下がる可能性は低いでしょう。Googleは「ユーザーに有益な情報を発信するサイト」を高く評価する傾向にあります。
アルゴリズムの結果を必要以上に意識せず、ユーザーがどのような情報を求めているか、ユーザーニーズや検索意図の把握に努めることが重要です。ユーザー視点に立った取り組みによって、記事やページの品質が高まり、検索順位にもいい影響を及ぼす可能性が高まります。

タイトルや見出し、本文にキーワードを盛り込むことは重要です。ただし、必要以上にキーワードを詰め込む行為は推奨できません。見出しや文章が読みづらくユーザーに不信感を与えるため、早期離脱を招く可能性が高まります。仮に離脱しなかったとしても、内容よりもキーワードが目立ってしまい、ユーザーの関心や購買意欲は高まらないでしょう。
たとえば、キーワードに「東京 居酒屋 個室」を選びます。タイトルが「東京でおすすめの居酒屋20選!個室付きの居酒屋も紹介」となっている場合、居酒屋が2回も出てくるため、ユーザーによってはしつこい印象を感じるでしょう。
タイトルを「東京でおすすめの居酒屋20選!【完全個室付き】」とした方が、すっきりとした印象を与えられます。早期の成果獲得を実現するには、ユーザーにとってわかりやすいタイトルや見出し、文章を作ることが重要です。

Googleのアルゴリズムが複雑になる前は、文字数の多い記事=良質な記事と評価される傾向にありました。ただし、文字数の多さはSEOでの順位に直接影響を与えません。Googleの見解でも上位表示のために、文字数を調整するのは意味のない行為と発表しています。
全体のボリュームを増やすために、キーワードと関連性の薄い情報や同じ内容を繰り返し掲載しても、検索順位は上がりません。かえって、ユーザーに「何を言いたいのかわからない文章」とネガティブな印象を与える可能性が高まります。
文字数は記事の品質を判断する上で、1つの基準と考えるべきです。記事全体の文字数の多さではなく、ユーザーにとって有益な情報を多く伝える姿勢が求められます。また、ユーザーにとって読みやすい記事を作成するため、冗長表現やキーワードの乱用も避けましょう。

公開済みのページや記事は定期的な更新が必要です。掲載時に最新の情報を反映していたとしても、数年後も掲載情報の内容が最新とは限りません。サイトの更新頻度が極端に低下すると、ユーザーがアクセスしても「最新の情報を取得できない」と思われてしまい、早期離脱を招く可能性が高まります。
ユーザーからの信頼を失わないよう、新しいページや記事の制作と並行して、既存ページの更新や既存記事のリライトを実施しなければなりません。更新作業やリライトのタイミングは上位表示ができていない、以前よりも検索順位が低下しているときなどがあげられます。

検索エンジンからの流入数を増やすため、記事やページ数を増やす施策は意味があるといえます。ただし、検索ボリュームやユーザーの検索意図を把握せず、やみくもに記事を増やしても検索エンジンやユーザーからの評価は高まりません。ユーザーにとって有益な情報が少ないため、かえってサイトへの評価や信頼性が低下します。
サイトへの評価を高めるには記事やページの数ではなく、情報の質を意識することが重要です。ユーザーの検索意図やニーズを把握し、記事の内容に反映しましょう。

Googleのガイドラインに違反した場合はスパムとみなされ、ペナルティによって順位低下やサイトの非表示を招くおそれが生じます。Googleのガイドライン違反に該当する行為は、以下のとおりです。
・キーワードの乱用
・誇張表現
・誤解や不安を与える表現
・低品質な記事の量産
・他の記事から内容をコピー
・不正な被リンク獲得
・広告の過剰掲載
・サイト運営者の情報が未記載
・独自性や専門性に欠ける記事
上記に該当する行為をしないよう、注意が必要です。

外部サイトで自社サイトへのリンクを貼られると、「信頼できるサイト」とみなされて検索エンジンやユーザーからの評価が高まります。ただし、無料のブログサービスを利用し、複数のURLから自社サイトを被リンクする行為はGoogleのガイドライン違反に該当します。Google側も自作自演で被リンクを獲得する行為は把握しており、SEOでプラスの評価が下されることはありません。
以下に該当する行為は、ペナルティの対象になるおそれがあるため、避けましょう。
自社サイトと関連性の低いWebサイトからのリンク
短期間で大量の被リンクを獲得
1つのページや記事に大量のリンクが掲載
サーバーと同じIPアドレスを使用

早期の成果獲得を実現するため、以下5つの点を意識しましょう。
検索ボリュームだけに注目して、キーワードを選ぶのは避けましょう。
検索ボリュームの多いキーワードは自社サイトが上位に表示されると、多くの集客が見込めます。ただし、競合数も多いため、上位表示の難易度も高くなります。サイトを立ち上げて間もない場合はロングテールキーワード、ある程度の期間SEO対策に取り組んでいる場合は、ミドルキーワードを選ぶのがおすすめです。
ともにビッグキーワードと比べて競合数が少ないため、SEO対策を長期的に取り組んでいくと、上位表示を実現できる可能性が高まります。
キーワードの内容ではなく、ユーザーの検索意図を理解することが重要です。
検索意図とは、ユーザーが検索エンジンを利用する目的です。検索意図の把握によって、ユーザーがどのような課題を抱え、どのような情報や商材を求めているか、可視化できます。ユーザーニーズを反映した記事やページの作成によって、アクセス数や成果の獲得数が伸びる可能性が高まります。
ユーザーの検索意図を理解する方法は、上位サイトの構成やサジェストキーワード、共起語の分析など、さまざまです。複数の方法を実践し、検索意図の理解に努めましょう。
アクセス解析によって、自社サイトが抱えている課題を把握することが重要です。「アクセス率が低い」や「コンバージョン率が伸びていない」など、課題の内容によって実践すべき施策は異なります。
アクセス解析では、GoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールを利用するのがおすすめです。Googleアカウントを持っていれば、ともに無料で利用できます。
Googleアナリティクスは、ユーザーの流入経路や属性、サイト内での行動傾向を分析できるツールです。平均ページ滞在時間や離脱率など、各指標から既存サイトの課題を可視化できます。
一方、Googleサーチコンソールは、Googleでの検索キーワードや自社サイトの順位、クリック数などを分析できるツールです。SEO対策の効果が出ているか、確認するために不可欠なツールといえるでしょう。
SEO対策は内部対策と外部対策、大きく2つに分類できます。内部対策は、サイト全体の構造や情報の中身を見直す対策です。内部対策によってサイトの利便性や情報の質を高め、良質な顧客体験の提供につなげます。内部対策に該当する施策は、以下のとおりです。
・タイトルタグや見出しタグの調整
・パンくずリストの設定
・内部リンクの最適化
・ディスクリプションの見直し
・XMLサイトマップの作成
・複数のURLを1つに統一
・robots.txtの設定
SEO対策に取り組む前に、Googleが重視するE-E-A-Tとユーザーファーストの考えを理解しておきましょう。E-E-A-Tは記事やページの中身を評価する上で、重要視している項目の1つです。E-E-A-Tは以下の単語から頭文字を取った言葉になります。
Experience(経験)
Expertise(専門性)
Authoritativeness(権威性)
Trustworthiness(信頼性)
誰が書いたかわからない記事よりも、特定の分野に精通した専門家が執筆・勧誘した記事を高く評価し、信頼するとの考えです。専門家が記事を書かない場合でも、筆者の体験談や論文や実地調査の資料などを記載すると、記事の信頼性を高められます。E-E-A-Tは金融や医療、健康などを扱う場合、評価に反映されるため、注意しましょう。
また、ユーザーファーストはユーザーにとって有益なだけでなく、サイトの使いやすさも含まれています。サイトの利便性を高めるため、サイトレイアウトの見直しやページ表示速度の改善などへの取り組みも必要です。
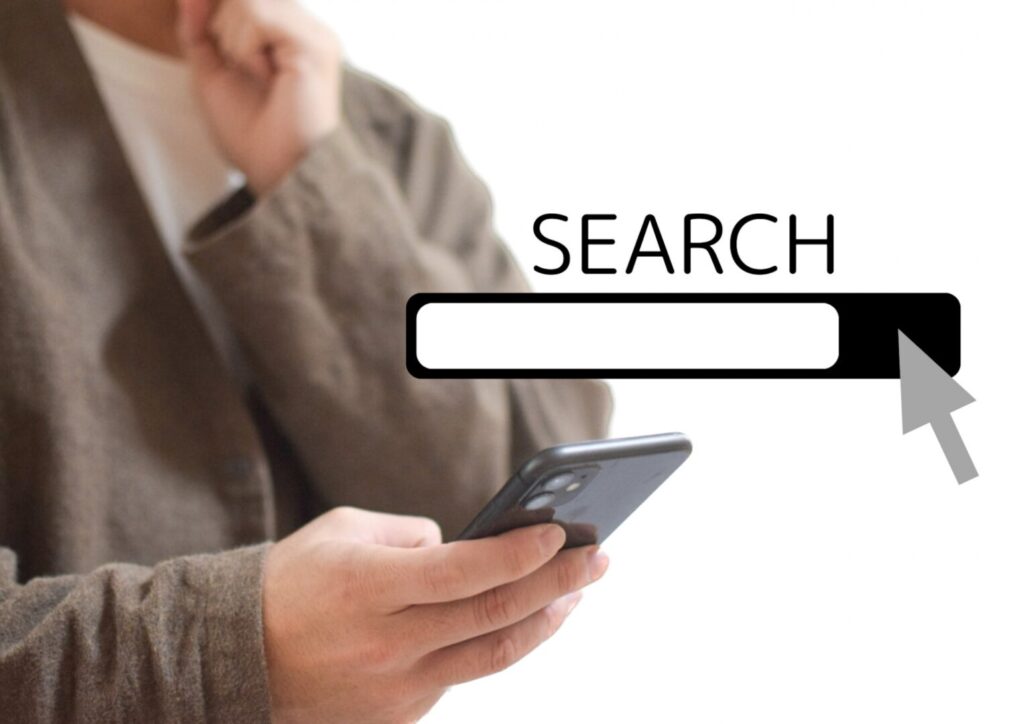
SEO対策自体に「意味がない」わけではありません。短期間での成果獲得が難しいのが、正しい認識です。キーワードの見直しや検索意図の把握、内部リンクの最適化など、内部対策を重点的に実施し、早期の成果獲得を目指しましょう。
ただし、SEO対策に取り組むリソース確保に不安を抱えている企業もあるでしょう。従業員の業務負担軽減と早期の成果獲得を実現するため、SEO対策会社に依頼するのも1つの選択肢です。
株式会社なかみは福岡県に拠点を置き、SEO対策やオウンドメディア支援などを実施している制作会社です。旅館や飲食店、ケア医療開発会社など、さまざまな業種の企業に利用されています。金額も比較的リーズナブルな価格に設定されており、予算確保に不安を抱える企業も安心して利用できるでしょう。
SEO対策で思うように成果が得られず悩んでいる方は、株式会社なかみにご相談ください。